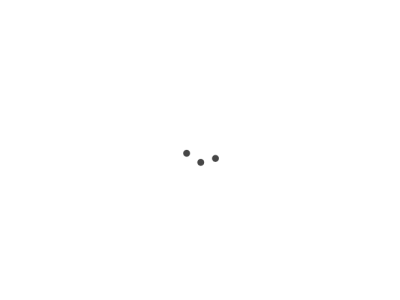スケジュールナースを使いこなすのに必要なスキルは?
の記事のように、プログラミング能力と国語力は、相関があるとされています。 スケジュールナースを使う上においても同じことが言えると思っています。プログラミング能力やITスキルは、敢えて言うと必要ではありません。それよりも、大きいのは国語力だと感じています。 というのは、実は、皆さんは、「制約プログラム」をGUIで書いています。コンピュータに指示するというのは、GUIではありますが、言葉で指示をしていることに同じです。言葉なしでは、一切動きません。 言葉という指示があって、スケジュールナースは、動きます。
仕様とは?
スケジュールナース内では、制約を書くことによって解を絞り込んでいきますが、その制約の元になっているのは、お客様自身が記述する仕様です。
部外者にご自分がつくる勤務表のルールを説明してみてください。それが「仕様」です。部外者ですから、部内の暗黙ルールは何も分かっていません。何も分からない部外者に、分
かるように言葉で伝えること、それが仕様になります。
その仕様文書を手に入れることが出来れば、誰もが、同じく内容を理解することが出来る、違う場所で、同じ勤務ルールを再現出来る、ということになります。
仕様は、誰が受け取っても、別な解釈を生まない、ことが重要です。必要にして十分かつ正確な情報伝達文書、それが仕様になります。
仕様はソフトウェアに依存しません。またプログラミング言語で記述されるものでもありません。日本語という国語で記述されます。
制約とは?
「ああしたい」、「こうしたい」とする思いは、制約という形でコンピュータに指示します。お客さまの「仕様」を、翻訳したものが「制約」です。
制約は、ソフトウェアに依存します。
言うなれば、スケジュールナースに対する「こういう解が欲しい」という指示が「制約」です。「制約は、一つ書けば、「求解」 ⇒「解」と 直ぐに、その制約結果を確認することが出来ます。
プログラミングは、一定の手続きを書かないと動いてくれませんが、一つの「制約」を書くだけで、その場で直ぐ動作を確認出来るところが違います。そうした制約を書き連ねることによって、欲しい解を絞りこんでゆくシステムが、スケジュールナースです。
最後は人間
スケジュールナースは、仕様ではなく、制約で動くソフトウェアです。従い、お客さまの仕様を、コンピュータに分かる言葉、スケジュールナースの「制約」に変換する必要があります。この部分は、将来AI(モデリングのAI化)が担う可能性があります。AIは、急速な進歩は認められますが、モデリングについては、未だ研究段階であり、夢の域をでません。また、如何にAIが発 達しても、最後は人間が管理しなければいけない、というのは将においても変わることはないでしょう。 欲しい解と実装との間に齟齬が生じたとき、何が正しいか?を言えるのは、AIではなく仕様を熟知している管理者になります。
仕様記述の傾向
ユーザさんの中で、お医者さんやら看護師勤務表を作っておられる方がいらっしゃいます。この方は、現役ではないのですが、いわゆる事務屋さん、だと思います。 そういう方が、畑違いの仕様をまとめて提示してくれていて、非常に助かっています。で、その力の源泉は国語力であると思う次第です。 プログラムでも、最初からコーディングすることはありません。何を実現するかというのは、企画書や仕様という日本語という言葉で形にすることで明示することから始まります。概念や目的等、抽象的な要件は、日本語という言葉から始まります。 このユーザさんのように、事務または事務長さんであるユーザさんは結構多いと思います。(訪問クリニック、産科クリニック、脳神経外科クリニック、数病棟の公立病院等、サポート経験からの推測です。) 人と人とのコミュニケーションに長けているということ、人の話を聞くこと、理解してまとめること、これは、全て国語力です。なので、別に看護師長である必要はない、ということだろうと思います。勿論、看護師長自身が使いこなせれば、それがベストですが、制約をメンテナンスする人が、看護師長である必要はありません。 男性か女性かという点においては、経験上、男性の方が国語力の優位性が高いと思います。何故かは分かりません。男性の方がロジカルである傾向があるからかもしれません。 どんなにITリテラシーに疎くても、国語力とやる気さえあれば、サポート出来る自信はあります。言葉のコミュニケーションさえできれば、必ず前に進めることが出来るからです。
最近の傾向
今まで、勤務表というのは、師長が作ってそれで終わりであり、誰も師長の作成方針は知ることがない と思っていたのですが、その職場ではそうではなく、あるユーザさまに次のように教えて頂きました。
■副師長や、主任が勤務表を作成する。作成後に師長が承認をする場合があります。
勤務表作成に複数人が関わる場合、コミュニケーションが必要になります。
コミュニケーションが生じると、思考の見える化と、制約の共有が必要になります。
メリットとしては、
・副師長や主任が勤務表を作成した後で、師長に「ここが違う」「ここのメンバーがよくない」と言われることをなくせる
・複数人いる副師長や主任が、交代で作成する場合、「求解」のクリックで勤務表が作成されるので、誰がつくっても同じ質が保てる。
・異動で勤務表の作成者が変わっても、ファイルを引き継ぐことと、設定した制約の意図を申し送るだけで済む
確かに、複数人で作成するやり方は、移動してきた看護師長が、その病棟の各スタッフの力量を未だ把握していない場合でも有効だと思います。 過去にあった、
看護師長の依怙贔屓問題
個別スタッフの特殊対応
等も複数人で共有することによって、より俯瞰的公平が担保されるということだと思います。何より師長の負担が減り、勤務表という形で、チームとしてのベクトルを揃える効果が期待できます。
国語の達人
ちなみに、今までに出会ったなかで、国語の達人と思うのは、弁理士さんです。特許の請求項をクレームと言うのですが、クレームでは、日本語で論理的なことを漏れなく明確に記載する必要があります。私が書いたクレーム原案は、殆ど跡形もなく添削されて別なクレームになるのが普通です。それは、特許クレームという一見複雑怪奇な文章ではありますが、見事に精緻で一分の隙もない文にする日本刀の研師のような作業です。これを成すには国語力、ということをおっしゃっていたのを思い出しました。 その弁理士さんは、推敲の際、句読点を区切りながらクレームをよく音読していました。正しいかどうか常に反芻しながら頭を回転させていたのでしょう。で、
■スケジュールナースで制約が思い通りに動かないとき、制約を音読してみる、
というのをお勧めしています。
自分が今書いた制約が、確かに意図通りであるか?反芻することで、バグを発見できるかもしれないからです。